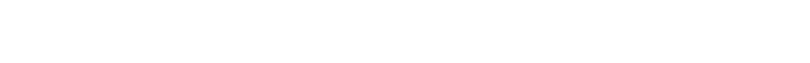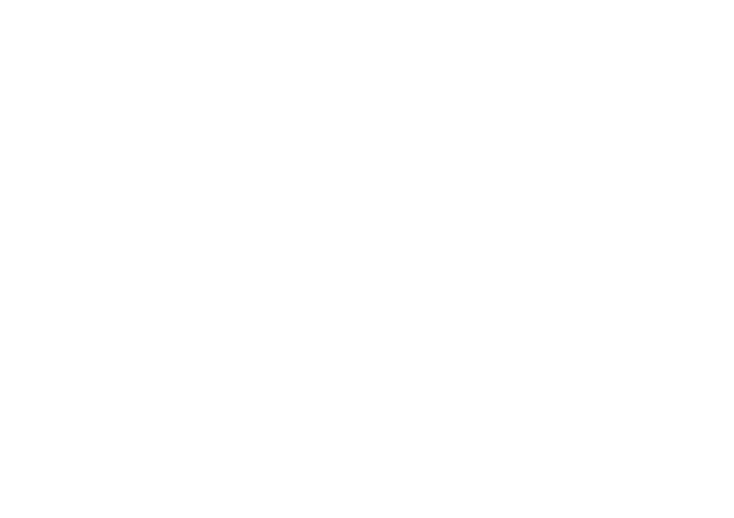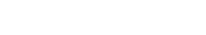研究代謝・行動生理学理研ECL研究チーム
はじめに
誰もが目にしたことのある昆虫である蚊は、ご存じの通り、ヒトや動物(宿主)から血を吸います。不快な羽音や痒みを残すだけでなく、さまざまな感染症の病原体を血管内に送り込み、ヒトを最も多く死に至らしめている動物とも言われる厄介な存在です。古くから蚊の行動や生態に関する記述や、根絶へのあらゆる試みがなされてきましたが、「蚊に刺されない世界」はいまだ実現していません。そのため現在も、蚊の制御を目指した多角的な研究が世界中で続けられています。
当研究室では、蚊の吸血を軸に、
- 1. 病原体が宿主に送り込まれる根源となる吸血行動はどう制御されるか
- 2.吸血後に体内で血液がどのように卵成熟に利用されていくのか
に注目し、蚊のバイオロジーをより深く理解することを目指しています。得られた知見は、将来的に蚊の吸血行動を制御するだけでなく、生殖プロセスに介入して卵産生を調節するような応用にもつながることが期待されます。
さらに、蚊が血液中の栄養成分を消化・吸収・代謝して利用する仕組みは、他の生物が食餌から得た栄養を生命活動に利用する過程と多くの点で共通しています。したがって、蚊の血液代謝を解明することは、蚊の理解にとどまらず、生物一般に共通する生命のしくみを探ることにもつながると考えています。

私たちがモデルとして研究に用いるのは、ヤブカ属のネッタイシマカです。亜熱帯・熱帯に生息するこの蚊は、ヤブカ属の中でも早くにゲノム解読が進み、分子生物学的な研究が盛んに行われてきました。日本には現在定着していませんが、身近でよく見かけるヒトスジシマカとは近縁の種です。研究室で安定的に飼育することができ、近年では遺伝子改変や編集も可能になりました。なお、吸血を行うのは産卵期の成虫メスに限られ、オスや羽化したばかりのメスは吸血を行いません。
1. 吸血行動を制御する機構の解明 - 蚊は血をどのように味わい満腹になるのか
蚊の吸血は数分で完了しますが、その間に体重が約2.5倍にもなる量の血液を取り込みます。非常にダイナミックでユニークな摂食様式です。
宿主の皮膚に着地した蚊は、口先の針を出し入れしながら移動することがあり、この動作は「プロービング」と呼ばれます。これは血管を探すための試し刺し行動で、うまく血管に到達すると急速に吸血を開始します。一方で、苦味などの忌避成分を感じると吸血をやめて針を引き抜きます。つまり、宿主に誘引された蚊がすべて吸血するわけではなく、「血が吸うに値するか」を味わって判断しているのです。
約60年前、宿主血液中のアデノシン三リン酸(ATP)が吸血を促す因子として同定されました。しかし、蚊がどのようにATPを受容しているのかはいまだ謎に包まれています。また、吸血をやめる仕組みについても未解明な点が多く残されています。お腹がはち切れる前に吸血を停止することから、腹部の伸展を機械的に感知している可能性は古くから示唆されてきましたが、その分子実体は明らかではありませんでした。
私たちは最近、吸血中に宿主血液の凝固反応で生じるフィブリノペプチドが、吸血をやめさせる機能を持つことを発見しました。このペプチドが存在すると、蚊は満腹に至る前に吸血をやめます。すなわち、蚊は腹部の伸展といった機械的なシグナルに加えて、腸でこのペプチドを感知することによって、吸血を終了させるタイミングを調整している可能性があります。
私たちは、蚊が口や腸で宿主の血液成分をどのように感じ取り、吸血の開始と終了を制御しているのか、さらには苦味などの忌避成分や他の味をどのように認識しているのか、その仕組みの解明を目指しています。


2. 蚊はどのように血の栄養成分を卵成熟に利用するか – 吸血モードと卵成熟モードの切り替え
メス蚊は吸血から約3日後に、およそ100個の卵を産みます。吸血前の卵巣には未成熟な卵母細胞が存在しており、吸血を契機に卵黄の合成・充填が進んで成熟卵へと発達します。産卵後は、幹細胞由来の次の卵母細胞が未成熟のまま休止し、次の吸血によって発達を再開します。つまりメス蚊は、生涯を通じて、複数回の吸血を行い、未成熟卵を抱えて宿主を探索する「吸血モード」と、取り込んだ血液を用いて卵を成熟させる「卵成熟モード」を行き来します。とりわけ、卵成熟モードのメス蚊は新たな血液を必要としないため、宿主への誘引行動を示しません。卵成熟の仕組みを解明することは、卵形成を通じた次世代数の制御に資するだけでなく、蚊を人為的に「卵成熟モード」へ切り替え、宿主誘引そのものを抑える戦略にもつながります。
卵成熟は複数の臓器とホルモンの協調で進行します。吸血により血液が腸へ取り込まれると、脳から卵巣へ複数のホルモンが放出され、これを受けた卵巣は脂肪体(哺乳類の肝臓および白色脂肪組織に相当)に、脱皮ホルモンとして知られるエクダイソンを分泌します。エクダイソン刺激によって脂肪体で卵黄合成が開始され、合成された卵黄は卵巣へ運ばれて未成熟卵に取り込まれます。こうして、脳・腸・脂肪体・卵巣、そしてそれらをつなぐ血リンパが連携し、卵成熟が円滑に進みます。
腸内の宿主血液は約50時間かけて段階的に消化され、その一部は卵成熟開始のシグナルとして機能し、別の一部は卵黄合成の原料となります。エクダイソンを中心とする卵黄合成の理解は進んでいるものの、卵成熟モードにおける宿主誘引抑制のメカニズムや、「吸血モード」と「卵成熟モード」を切り替える仕組みには、なお未解明の点が残されています。
当研究室は、この二つのモード切り替えの制御機構に着目し、神経科学・代謝・内分泌の視点からその本質に迫ります。とくに宿主血液に豊富なアミノ酸とタンパク質に注目し、従来ひとまとめに扱われがちだった20種のアミノ酸について、各アミノ酸の固有の動態、時間依存的な代謝、特異的機能を明らかにしつつあります。さらに、卵成熟の時間軸に沿って臓器間を循環するホルモンを包括的に解析し、代謝・内分泌状態が行動に及ぼす影響を解明することを目指しています。