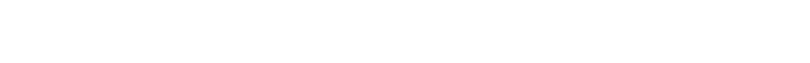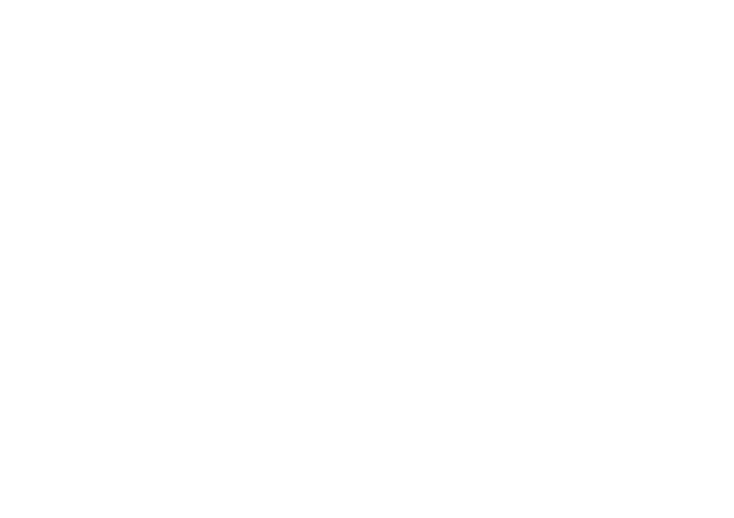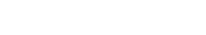「高校教職員のための発生生物学実践講座」を開催
2018年10月10日

線虫C. elegansは、極めて研究に有用な生物であると同時に、飼育が簡単で通常の顕微鏡の下で扱えるため、最小限の実験機器さえあれば、誰でもC. elegans を使った研究を始めることができます。こうした扱いやすさゆえに、近年、研究者だけではなく、高校の教育現場も線虫に注目するようになってきています。
そこで9月29日(土)に、理研BDRの神戸地区において、高校で生物を指導している教員に向けて、C. elegansを用いた実践的な講習会「高校教職員のための発生生物学実践講座」を開催しました。兵庫県、大阪府を中心に広く関西エリアから16名の高校の教員が集まりました。
本イベントは日本発生生物学会(JSDB)と兵庫県高等学校教育研究会生物部会との共催イベントで、JSDB会員である関西学院大学の西脇清二教授が教材の監修と実験の指導を行いました。

まず西脇教授による線虫の概要と実験手技についてのレクチャーがあり、その後、早速、実習に入りました。様々な変異形質を示す変異株を見分けることから始め、線虫の扱いの基本である、線虫を一匹ずつ拾い上げて新しいプレートに移す手技を学び、変異株の雌雄同体と野生株のオスを掛け合わせる実験を行いました。また、デモ実験では緑色蛍光タンパク質(GFP)を組み込んだ線虫の観察を行いました。
また、兵庫県高等学校教育研究会生物部会のメンバーが中心となって、高校の教室で普段使われている生物顕微鏡などを会場に設置し、生物の授業で実践可能な実験として、線虫の初期胚のプレパラート作成と発生の継時観察などを行いました。
BDRの西田栄介センター長による講義も行われ、寿命が伸びる変異株などを用いた研究の説明に参加者からは多くの質問が寄せられました。後半はサイエンスカフェ風のセッティングにかえ、教育など、より広範な話題について、ざっくばらんに討論を行いました。
開催した週末には関西エリアに台風が近づいていたため、当初2日間の予定だった講習が急遽1日のみの日程に変更され、2日目に予定していた実験を1日目にくり込んだため、スケジュールはかなりきついものになりましたが、受講者らは朝から夕方まで集中して実習に取り組みました。
本プログラムの姉妹編として、12月25日に「高校生のための発生生物学実習講座」が開催される予定です。今回参加した教員の中から選ばれた企画実行委員が教材の内容を高校生向けにアレンジし、当日の運営および生徒の指導を行います。