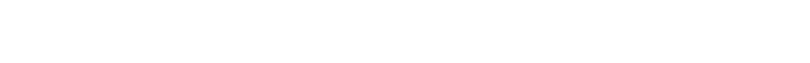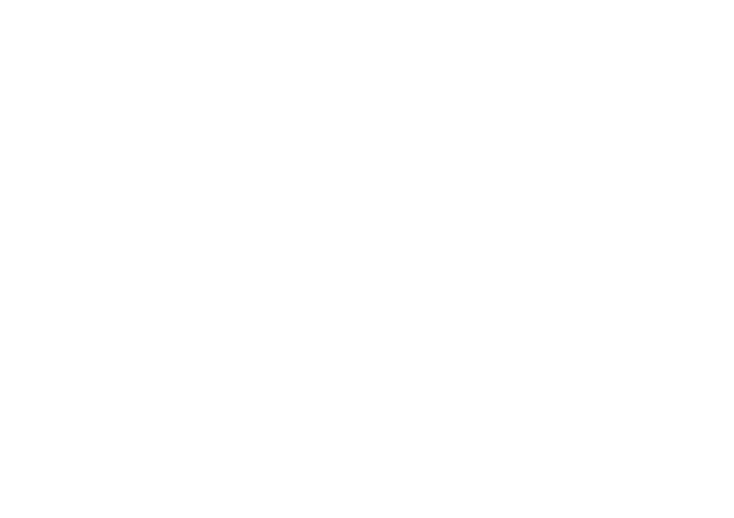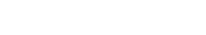サイエンスカンバッジ
「これはなに?」からはじまるカガク

細胞の性質のちがいを蛍光色でとらえる
わたしたちの体の中には性質のことなる様々な細胞があります。細胞の性質を決めている分子の活性を可視化するために有効なのが、蛍光物質をつかった実験です。たとえば3種の分子の活性を赤、青、緑の三つの蛍光で光らせると、細胞の性質の違いによって、さまざまな色の細胞が現れます。
>> 詳しい研究内容

新しいモデル動物、ソメワケササクレヤモリ
陸上生活をする脊椎動物の研究対象として、これまでの哺乳類と鳥類に加えて、最近はは虫類も注目されています。理研BDR ではソメワケササクレヤモリをモデル動物として飼育・繁殖を継続していて、遺伝子改変技術も利用できるようになりました。
>> 詳しい研究内容

細胞の“利き手”を決めるアクトミオシンリング
私たちの体は左右対称に見えても、内臓の位置や形は左右非対称な場合があります。これは細胞や分子のもつ非対称性とも関係していると考えられています。ある種の細胞では細胞質や核が時計回りに回転していて、この回転の駆動力を生み出しているのが、アクトミオシンリング(緑色)というタンパク質でできた輪っかであることがわかりました。
>> 詳しい研究内容

理化学研究所生命機能科学研究センター
多彩な分野の研究者が、さまざまな研究を実施している生命機能科学研究センター。さまざまなモデル動物と、分子、細胞、組織レベルでの研究についてのイメージ図です。
>> 詳しい研究内容

受精卵の分割と染色体分配異常
哺乳類の受精直後は、染色体分配異常の頻度が高いことが知られています。受精直後のマウス胚の細胞一つ一つのDNA複製を調べたところ、4細胞期にDNAの複製様式が変化し、染色体分配異常が高頻度に生じていることがわかりました。(赤や黄色に光っているのは細胞核)
>> 詳しい研究内容

染色体は外側にあるものほど伸びにくい
細胞分裂の際には、微小管が染色体(ブルー)にくっつき両極へ均等に引っ張ることで染色体が伸びますが、外側の染色体ほど、伸びにくいことがわかりました。この空間的張力の微妙なバランスが加齢や不妊とどう関係しているか研究しています。
>> 詳しい研究内容

ヤンバルクイナ、背骨の数にはルールがある
鳥の背骨の数は種によって大きく違うことが知られていますが、我孫子市鳥の博物館に所蔵されたさまざまな鳥類の骨格標本を調査した結果、首と胸の骨の合計は腰より後ろの骨の合計とだいたい一致するというルールがあることが分かりました。このルールは、飛行能力と関連して恐竜から鳥への進化の過程で獲得された可能性があります。
>> 詳しい研究内容